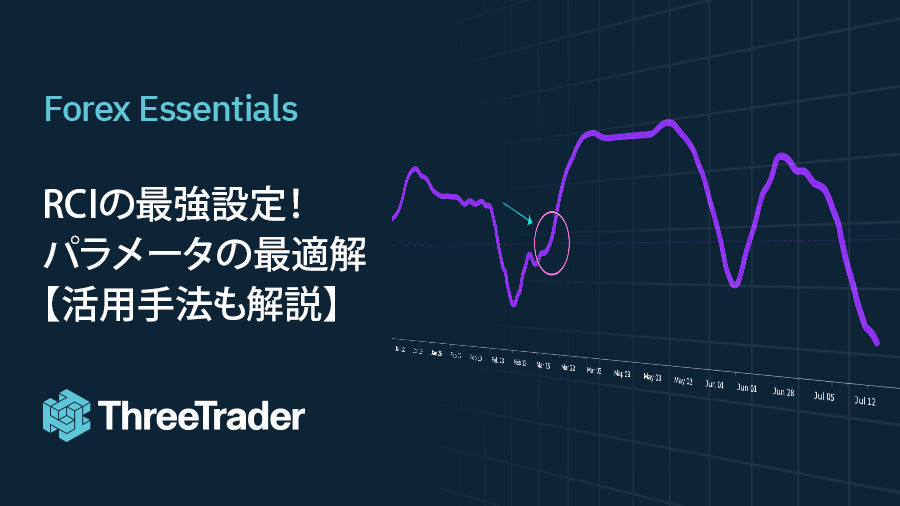FXのN波動とは?見つけ方5選【N字理論をトレードに活用!】
FXトレードで勝つために大切なのは、「今の相場がどっちに動きそうか」を見きわめることです。 しかし、毎日のチャート(価格の動き)を見ているだけでは、その流れをつかむのは難しいかもしれません。
そんなときに役に立つのが、「N波動」というチャートパターンです。
このN波動は、値動きがアルファベットの「N」に見えることから、その名前がついています。
「N」の形になるとき、相場は上がり続けるか、下がり続けるか、どちらかの流れが強くなっていることが多いです。 この形を見つけることで、「買うタイミング」「売るタイミング」をつかみやすくなります。
この記事では、
- N波動とは何か
- どうやって見つけるか(ローソク足の形やインジケーターの使い方など)
- 実際のトレードにどう使うか
などを、わかりやすく説明します。
この記事を読み終えた後には、N波動を自信を持って活用し、より精度の高いトレード判断ができるようになるでしょう。FXトレードの成功に近づくための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
FXのN波動とは?

N波動とは、チャートを見ながら相場の動きを予想するための、とても強力な分析方法です。多くのプロのトレーダーも実はひそかに使っている「テクニカル指標(チャート分析の道具)」の一つで、「N字理論」と呼ばれることもあります。
ここでは、N波動の特徴やパターンの種類について、詳しく説明していきます。よく似ていて間違えられやすい「E波動」との違いについても、わかりやすく解説します。
特徴
N波動とは、チャートの形のひとつです。
例えば、「上昇→押し目→再び上昇」や「下降→戻り高値→さらに下落」といった、3つの動きからできています。アルファベットの「N」のような形に見えるため、こう呼ばれます。
この形を知っていると、「今は買うべきか、売るべきか」の判断がしやすくなります。エントリーや損切りも決めやすくなるのがポイントです。
また、N波動を理解すると、だましに惑わされにくくなり、ムダなエントリーを減らすことができます。
N波動は、1分足から日足まで、どんな時間のチャートにも現れます。そのため、複数の時間を組み合わせて分析する「マルチタイムフレーム分析」にも使いやすく、初心者でも相場の流れをつかみやすくなります。
N波動の種類
N波動には、大きく分けて3つのパターンがあります。
- 上昇のN波動
→ 安値と高値が切り上がっていく形です。押し目が入ることで、順張りの買いタイミングがわかりやすくなります。 - 下降のN波動
→ 高値と安値が切り下がっていきます。戻り高値のあとに下落が続くため、売り戦略に役立ちます。 - もみ合いのN波動
→ 相場が上にも下にも動かず、レンジ内で動いているときに現れる形です。
このもみ合いの中では、「P波動」や「Y波動」といった少し変わった動きが見られることもあります。これらは、ブレイク(急な動き)が始まる前のサインになることもあるので、よく観察しておきましょう。
上昇のN

上昇のN波動は、相場が本格的に上昇トレンドに入るときに出やすいチャートの形です。
最初に価格が上昇して「高値」をつけたあと、「押し目」が入って少し下がります。そして次の上昇でその高値を超えると、上昇が本物かどうかを確認できます。さらにもう一度押し目が入り、三度目の上昇でさらに高値を更新すると、より強いトレンドとして意識されます。
この波形では、「安値」と「高値」がどんどん切り上がっていくのが特徴です。移動平均線との距離(乖離)や、押し目がどのくらい深いか、直近の高値をどれだけ更新したかを見ると、トレンドの強さを判断しやすくなります。
特に「押し目買い」を狙うときには、この形がとても役に立ちます。
下降のN
下降のN波動は、相場が下落トレンドに変わるときに見られる形です。
最初に大きく下落して「安値」をつけたあと、少し上がって「戻り高値」を作ります。しかしそのあと、また下がって安値を更新すると、下落の流れが本格的になるサインになります。

上記はドル円の4時間足チャートですが、大きな下降、調整の上昇という流れを繰り返していますね。
この波では、「高値」と「安値」がどんどん切り下がっていくのがポイントです。移動平均線が下向きだったり、戻り高値が浅かったり、安値を大きく更新したりする場合は、下落トレンドが強いと考えられます。
下降のN波動は「戻り売り」をするときにぴったりです。上がってきたときに慌てて買わず、流れに逆らわないことが大切です。
もみ合いのN
もみ合いのN波動は、相場が上にも下にも動かず、価格が狭い範囲を行き来している「レンジ相場」でよく見られる形です。

このときは、はっきりした上昇や下降のトレンドがなく、「高値」や「安値」の変化も小さくなります。チャート全体としては横ばいに動いているように見えます。
こういう場面では、大きく利益を出すのは難しいですが、短い時間で何度も売買する「スキャルピング」や短期トレードには向いています。もみ合いの中でできる小さなN波動を見つけて、コツコツと利益を積み上げるやり方が効果的です。
次に紹介する「P波動」や「Y波動」も、もみ合い相場の中でよく出る形なので、合わせて覚えておくと便利です。
もみ合いP波動のN
もみ合いP波動のNは、相場の動きがだんだん落ち着いてきて、値動きが小さくなっていくときに出てくる形です。チャートでは、高値が少しずつ下がり、安値はほとんど変わらないため、先が細くなる三角形のように見えます。

この中で小さな「N波動」が3つくらいできると、買いと売りの力がぶつかっている状態になります。そして、たまった力が一気に動き出すと「ブレイクアウト」が起きやすくなります。
このパターンを見つけると、次に「上に抜けるか」「下に抜けるか」のヒントになります。初心者にとっても、落ち着いた動きの中で売買タイミングを練習するのにぴったりです。
もみ合いY波動のN
もみ合いY波動のNは、相場がレンジの中で大きく上下に動いたあと、少しずつ落ち着いてくるときに見られる形です。P波動とは反対に、高値と安値の幅が広がっていくため、チャートは荒く不規則に動きます。

このときにできる3つの波で「N波動」が現れると、ブレイクアウトや急な反転が起こるサインになることがあります。タイミングが合えば短期売買のチャンスになりますが、間違えると損もしやすいため注意が必要です。
活用するときは、レジスタンスライン・サポートラインやオシレーター系の指標も一緒に使って、反転のタイミングを見極める力をつけましょう。
E波動との違い
E波動は、N波動と同じく相場の流れを分析するためのパターンですが、その構造と使い方には明確な違いがあります。
N波動が3つの波を通じてシンプルにトレンドの方向性を見極めるのに対し、E波動は一度終わったように見えるトレンドが再び動き出すときに現れる、より複雑で延長的な波形です。
E波動では、押し目や戻りの動きが不規則になりやすく、天井や底と見せかけて逆に伸びるようなダマシが発生しやすいため、より慎重な観察が必要です。このため、E波動を読み取る際には、単独ではなく他のテクニカル指標と組み合わせて判断するのが効果的です。
N波動と比較して扱いは難しいものの、相場の大きな転換点やブレイク前の動きを捉えられるチャンスもあり、上級者にとっては重要な判断材料となります。
N波動の見つけ方
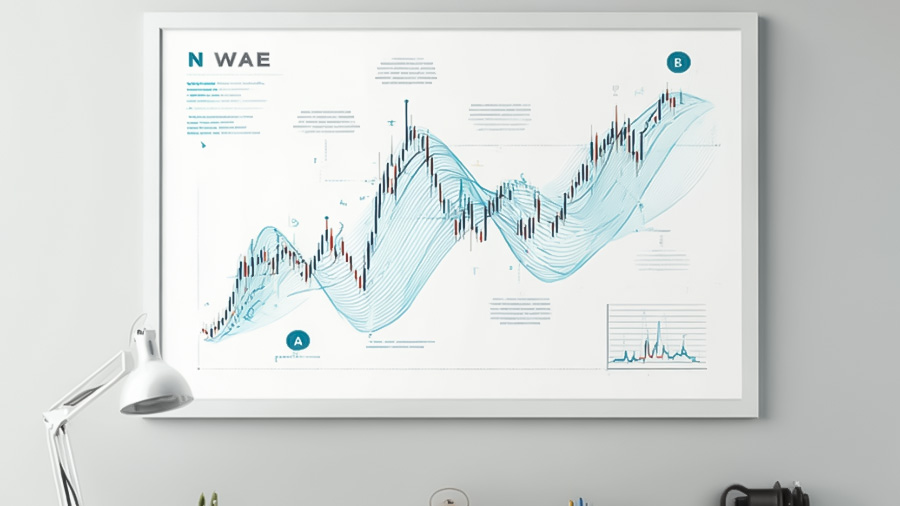
N波動を見つけられるようになると、相場の流れを早くつかめて、トレードの成功率が大きくアップします。
ただし、N波動はいつもはっきり見えるわけではありません。だからこそ、いくつかの視点から見て、しっかり判断することが大切です。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる5つの方法を紹介します。
・キャンドルパターン
・インジケーター
・ダウ理論
・レジサポライン
・フィボナッチ
上記の方法をひとつずつ、詳しく解説していきますね。
キャンドルパターン
N波動を見つける基本的な方法のひとつが、ローソク足(キャンドル)の形や並びに注目することです。たとえば上昇のN波動では、大きな陽線のあとに小さな陰線や十字線が入り、そのあと高値を更新する動きがよく見られます。これは「押し目をつけて再上昇している」という典型的なパターンです。
反対に下降のN波動では、大陰線のあとに一度戻り(陽線)が入ってから、さらに安値を更新する流れが確認できます。
また、ピンバーやエンゴルフィングといったローソク足の反転サインが押し目・戻りの位置に出た場合、次の波がどちらに動くかを予測する手がかりになります。
インジケーター
インジケーターを使うと、相場の流れを視覚的かつ客観的に判断できるため、N波動の確認にとても役立ちます。
たとえば、移動平均線(MA)ではゴールデンクロスやデッドクロスがトレンドの転換点を示し、MACDのシグナル交差もトレンドの始まりを教えてくれます。
また、RSIやストキャスティクスなどのオシレーターを使うと、押し目や戻りのタイミングをより正確に判断できます。インジケーターは一つだけで判断せず、ローソク足やチャート形状と組み合わせることで、N波動の信頼性が高まります。複数の指標を重ねてチェックすることが、より正確な分析につながります。
ダウ理論
ダウ理論は、「高値と安値の切り上げ・切り下げ」に注目するシンプルな考え方で、N波動を見つける際にもとても役立ちます。
一例として、高値と安値がともに切り上がっていれば上昇トレンド、逆に切り下がっていれば下降トレンドと判断できます。これはN波動の動きと一致しており、3つの波(上昇・押し・再上昇/下降・戻り・再下降)の中で、その流れを確認することでトレンドの継続や転換を判断しやすくなります。
ダウ理論の良いところは、相場の基本ともいえるシンプルなルールで、多くのトレーダーに使われているため、売買判断の裏付けとしても信頼性が高い点です。
ただし、短期的には「だまし」も起こり得るため、移動平均線やインジケーターなどと併用して分析するのが効果的です。
レジサポライン
レジスタンスラインとサポートライン、いわゆるレジサポラインを使ってN波動を見つける方法は、相場の反発ポイントやトレンドの押し・戻りを判断するのにとても役立ちます。
こうした場面では、上昇のN波動ではサポートライン付近で押し目買いが入りやすく、次の上昇につながるケースが多く見られます。逆に、下降のN波動ではレジスタンスラインが戻り売りの起点となり、下落の再開を確認しやすくなります。
また、レンジ相場でもレジサポラインが上下の壁として機能するため、N波動の小さな動きを捉えるヒントになります。重要なのは、そのラインが過去の相場で何度も反応しているかを確認し、信頼性の高い位置に引くことです。
これにより、N波動の形成されやすいポイントを見極め、エントリーや決済の判断に活かすことができます。
フィボナッチ
フィボナッチを使ってN波動を見つける方法は、押し目や戻りの深さを数字で把握できるため、初心者にもわかりやすく、エントリーや損切りポイントを論理的に決めやすいのが特徴です。
たとえば、上昇のN波動では、価格が38.2%や61.8%の水準まで押してから再上昇する場面がよく見られます。逆に、下降のN波動では戻りが50%付近で止まり、再下落に転じるケースが典型的です。
こうしたフィボナッチ比率は、多くのトレーダーに意識されているため、実際に価格が反応しやすいポイントでもあります。また、複数の時間足でフィボナッチを重ねてラインが一致する場所を探せば、信頼性の高い節目を見つけやすくなり、N波動の判断に役立ちます。
N波動を活用したトレード戦略

N波動を見つけられるようになったら、次は実際のトレードで利益を上げる方法を知りたいですよね。このセクションでは、N波動を活用したトレード戦略を紹介します。具体的には以下の3つです↓
・リバウンドポイントで仕掛けるスキャルピング手法
・精密な損切り/利確ライン設定手法
・延長パターンを利用した中長期トレード手法
上記は、短期で素早く利益を得たいトレーダー、リスク管理を徹底したい方、そして大きな利益を狙いたい方、それぞれに向けた手法です。あなたのトレードスタイルに合わせて戦略を選ぶことができます。
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
リバウンドポイントで仕掛けるスキャルピング手法
リバウンドポイントを使ったスキャルピング手法は、N波動の押し目や戻りの場面を狙って、短い時間で小さな利益を積み重ねていく方法です。
具体的には、上昇のN波動では、一度下がったあとに再び上がり始める「押し目」のタイミングで買いを入れ、少し利益が出たところですぐに決済します。逆に、下降のN波動では、一時的に上がったあとに再び下がる「戻り」の場面で売りを行い、短く利益を取るのが基本です。スキャルピングは取引時間がとても短いため、相場の動きをよく見てすばやく判断する力が必要です。
移動平均線やRSIなどのインジケーターを使えば、エントリーの目安がよりわかりやすくなります。自分が見やすい時間足を使って、N波動のリズムをしっかりつかむことが大切です。
精密な損切り/利確ライン設定手法
N波動を活用して損切りや利確のラインをしっかり決めることは、トレードでのリスクを抑えるうえでとても大切です。
押し目買いをする場合は直近の安値、戻り売りをする場合は直近の高値の少し下(または上)に損切りラインを置くと、相場が予想と反対に動いたときの損失を小さく抑えやすくなります。
一方、利確ラインはN波動の流れの中で、次に価格が到達しそうな高値や安値を目安に設定するのが基本です。
上昇のN波動なら前回高値付近、下降なら前回安値付近を目指すイメージです。さらに、フィボナッチや移動平均線を使えば、反転しやすい価格の目安がわかりやすくなり、より根拠のあるライン設定が可能になります。
あらかじめルールを決めておけば、迷いが少なくなり、感情に流されない安定したトレードにつながります。
延長パターンを利用した中長期トレード手法
N波動の延長パターンを活用した中長期トレード手法では、相場の大きな流れに乗りながら、より広い値幅を狙うことができます。上昇のN波動が何度も押し目をつけながら高値を更新していくような動きは、延長パターンの一例です。
このような局面では、移動平均線がしっかり上向きかどうかを確認することで、トレンドの継続性を判断しやすくなります。
分析には、日足や週足といった長めの時間足を使うと、短期的なノイズに惑わされず安定した判断が可能です。エントリー後は、フィボナッチ比率などを活用して押しや戻りの深さを測りながら、利確や追加エントリーのタイミングを探っていくと良いでしょう。
相場全体の流れをしっかり捉えることで、利益を着実に伸ばせる可能性が高まります。
N波動の注意点

N波動はトレンドの流れを視覚的に捉えやすく、多くのトレーダーに支持されている手法ですが、すべての局面でうまく機能するわけではありません。むしろ、その形にこだわりすぎて判断を誤るケースも少なくないのが実情です。
このセクションでは、N波動を使ったトレードで陥りやすい3つの注意点と具体的な対処法を紹介します。N波動の特徴と限界を正しく理解することで、戦略の精度と柔軟性を高めることができるでしょう。
まずは、N波動は「絶対的なものではない」というポイントから詳しく解説していきます。
絶対的なものではない
N波動は、相場のトレンドを視覚的にとらえやすく、初心者でも使いやすい分析手法です。しかし、あくまでひとつの見方に過ぎず、常に正確に機能するわけではありません。特に、突発的な経済ニュースやイベントが発生すると、N波動のパターンが崩れたり、想定と違う動きになることもあります。
また、同じチャートを見ていてもトレーダーによって波の捉え方が異なるため、解釈に個人差が出やすい点にも注意が必要です。N波動だけに頼っていると、期待通りに動かなかったときに損失を出すリスクが高まります。
そのため、N波動はあくまで補助的な分析ツールととらえ、移動平均線やインジケーター、ファンダメンタルズ分析と組み合わせて使うことが大切です。
対策
N波動を唯一の根拠とせず、移動平均線・MACD・レジサポライン・ダウ理論などと組み合わせましょう。また、経済指標や地政学リスクといったファンダメンタルズ要因もチェックし、相場全体の背景を理解したうえで活用するのが安全です。
レンジ相場では効果的ではない
N波動はトレンド相場において有効な分析手法ですが、レンジ相場ではその効果が大きく低下する傾向があります。
N波動は価格が一方向に動きながら押し目や戻りを形成することを前提としているため、値動きが狭く上下を繰り返すレンジ相場では波形が不明瞭になり、「だまし」のシグナルが多く発生してしまいます。
特に、レンジの上限や下限がはっきりしない場面では、高値や安値の切り上げ・切り下げも判断しにくく、N波動の起点を特定することが難しくなります。その結果、期待した方向に相場が動かず、早すぎるロスカットや不十分な根拠によるエントリーにつながりやすくなります。
N波動のシグナルを無理に追いかけることで、かえって損失を増やしてしまうこともあるため、レンジ相場ではN波動だけに頼らず、他の判断材料と併用する姿勢が必要です。
対策
価格が一定の範囲で動いていると感じたら、N波動による順張りではなく、上限での売り・下限での買いといった逆張りを意識しましょう。また、ブレイクアウトまで待つ・スキャルピングに切り替える・様子見するなど、相場に合った柔軟な対応が必要です。
時間軸によって解釈が変わる可能性がある
N波動は、見る時間軸によって形や意味が大きく変わることがあります。たとえば、週足や日足では明確な上昇N波動に見えるチャートも、5分足や15分足で見ると複雑な波が交差し、逆に下降の流れに見えることがあります。
これは、時間軸によってトレーダーの売買行動や注目している水準が異なるためです。短期足での押し目や戻りが、実は長期足では一時的な調整にすぎず、逆張りになってしまうケースも多く見られます。
その結果、天井買いや底売りといった失敗を招く恐れがあるため、時間軸ごとの視点の違いを理解しておくことが重要です。
対策
「マルチタイムフレーム分析」が有効です。まず日足や4時間足などでトレンドの方向を確認し、その流れに沿って短期足でエントリーポイントを探しましょう。上位足の流れと合致しているかを常に意識することで、逆行トレードのリスクを減らせます。
ThreeTraderでN波動を活用

N波動は、相場の流れを視覚的にとらえるために非常に有効な分析手法です。しかし、「見えるだけ」では利益にはつながりません。
ThreeTraderのMT4/MT5を使えば、標準搭載のインジケーターや描画ツールを活用し、N波動を具体的なトレード戦略へと落とし込むことが可能です。
ここでは、初心者でも再現しやすい4つの実践手順を紹介します。ThreeTraderの取引ツールをそのまま使うことで、チャート分析→エントリー判断→利確まで一貫したトレードが実現できます。
手順①:「ZigZag」でN波動の構造を明確化
→ 高値・安値の流れを視覚的に把握する
ZigZagインジケーターを使えば、相場の山と谷が自動的に表示され、N波動の基本構造(A→B→C→D)が明確になります。
これにより、どの位置が押し目・戻りかを感覚でなく、視覚的に捉えやすくなります。
ThreeTraderのMT4/MT5では、ZigZag設定をテンプレート保存可能。他通貨ペアへの即時適用にも対応しています。
手順②:「フラクタル」で波の転換点をつかむ
→ 初動の反転ポイントを見逃さない
フラクタルインジケーターは、一定期間の中での高値・安値(山・谷)を自動的にマークしてくれます。
N波動の始まりや、押し目・戻りのタイミングを探るうえで心強い補助になります。
ThreeTraderは高速約定&低スプレッド。こうした小さな転換点を狙ったスキャルピング戦略との相性も抜群です。
手順③:「フィボナッチ・リトレースメント」でC点を特定
→ 押し目・戻りの深さを数値で判断する
上昇のN波動では、A→Bの上昇幅に対して、38.2%〜61.8%の押しがC点の目安となります。
この水準を明確に把握できれば、エントリーのタイミングを絞り込むことができます。
ThreeTraderのMT4/MT5では、ワンクリックでフィボナッチ描画が可能。複数の時間軸でラインが重なれば、より強い根拠として活用できます。
手順④:「フィボナッチ・エキスパンション」で目標価格(D点)を予測
→ トレードの出口戦略をロジカルに設定
A→B→Cの3点を指定するだけで、**D点(FE100%、FE161.8%など)**の候補価格が自動的に表示されます。
「どこまで伸びるか」を数値で見積もれるため、部分利確やトレーリングストップの戦略も立てやすくなります。
ThreeTraderでは複数の利確ラインを同時に描画できるので、柔軟な出口設計が可能です。
まとめ|FXのN波動
本記事では、FXトレードにおけるN波動の基本から応用まで詳しく解説してきました。N波動とは、チャート上で「N」の形状に似た動きを示すパターンであり、相場の転換点を予測するのに非常に有効なテクニカル分析手法です。
上昇N波動、下降N波動、もみあいN波動など複数の種類があり、それぞれの特徴を理解することがトレード成功の第一歩となります。また、E波動との違いを理解することで、より精度の高い分析が可能になります。
N波動の見つけ方としては、キャンドルパターン、各種インジケーター、ダウ理論、レジスタンス・サポートライン、フィボナッチなどの手法が効果的です。これらを組み合わせることで、より高い確率でN波動を特定できるようになります。
実際のトレードでは、リバウンドポイントを狙ったスキャルピング、精密な損切り・利確ラインの設定、延長パターンを活用した中長期戦略など、さまざまな戦術に応用できます。
ThreeTraderの充実したツールと組み合わせることで、N波動分析の精度をさらに高めることができます。今日からN波動を意識したトレードを始めて、あなたのFX取引に新たな武器を加えてみてはいかがでしょうか。